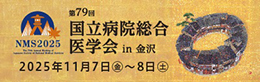病む人の気持ちを大切にして、
安全で最善な医療を提供します。
外来のご案内
- 新患の方
-
-
予約不要(※受付8:30 ~ 11:00)
呼吸器内科、呼吸器外科
-
完全予約制(※予約受付にお電話いただき予約をお願いします。)
脳神経内科、物忘れ外来、リウマチ科(膠原病)、
皮膚科、放射線科 -
休診日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
外来担当医表はこちらから
-
予約不要(※受付8:30 ~ 11:00)
- 再来院の方
-
- 原則予約制のみ担当医が指定した日時にご来院ください。
-
重要なお知らせ(令和7年4月2日更新)
福岡県大牟田市・国立病院機構所属の医療機関
外来のご案内
- 新患の方
-
-
予約不要(※受付8:30 ~ 11:00)
呼吸器内科、呼吸器外科、循環器内科
-
完全予約制(※予約受付にお電話いただき予約をお願いします。)
脳神経内科、物忘れ外来、リウマチ科(膠原病)、皮膚科、放射線科
-
休診日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
外来担当医表はこちらから
-
予約不要(※受付8:30 ~ 11:00)
- 再来院の方
-
- 原則予約制のみ担当医が指定した日時にご来院ください。
SCROLL
大牟田病院についてABOUT US
新着情報NEWS
病院からのお知らせ
- 2025.04.01 呼吸器内科外来休診のお知らせ(令和7年4月11日)
- 2025.02.06 X線透視装置更新に伴う工事のお知らせ
- 2025.01.30 薬剤部見学会のご案内(令和7年度)
- 2025.01.22 5病棟の休棟について
- 2025.01.01 院長新年挨拶
- 2024.12.19 【認知症医療センター】認知症の講演会“認知症カフェフェスタ”のご案内
- 2024.10.15 【認知症医療センター】認知症の講演会”映画上映会”、”市民公開講座”、”回想法で認知症予防”のご案内
- 2024.10.01 【重要】第三者委員会による提言書の公表について
- 2024.09.17 【認知症医療センター】認知症“家族支援”~認知症ケア教室(レビー小体型認知症)~のご案内
- 2024.09.12 【重要】当院職員及び元職員の書類送検について
- 2024.09.02 【重要】当院職員による入院患者さまへの虐待事案について
- 2024.08.26 認知症医療センター 第3回GYANよかばいDライトフェス(9/28)のご案内
- 2024.08.15 CT装置更新工事に伴う検査停止のお知らせ
- 2024.08.02 【認知症医療センター】認知症“家族支援”~認知症ケア教室~ のご案内
- 2024.07.23 電話自動応答・録音システムの導入及び非通知電話の対応について
- 2024.07.22 電話回線工事に伴う代表電話等の不通について
- 2024.07.18 後発医薬品使用体制のご案内
- 2024.06.24 【認知症医療センター】アルツハイマー病による軽度認知障害~軽度の認知症の治療薬「レケンビ注」による治療を開始しました
- 2024.06.07 【認知症医療センター】 事例検討会と認知症に関する研修会のご案内
- 2024.03.26 薬剤部見学会のご案内
来院される方へ
- 2025.01.27 面会制限解除のお知らせ
- 2025.01.10 面会中止のお知らせ
- 2024.08.27 面会について
- 2024.06.01 外来担当医表を更新しました(令和6年6月1日現在)
医療関係者の方へ
- 2024.05.07 看護助手(非常勤職員)募集のお知らせ
- 2024.03.01 医療社会事業専門員(非常勤職員)募集のお知らせ
- 2023.09.22 臨床検査技師(期間職員)募集のお知らせ